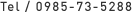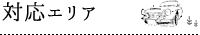木材へのこだわり
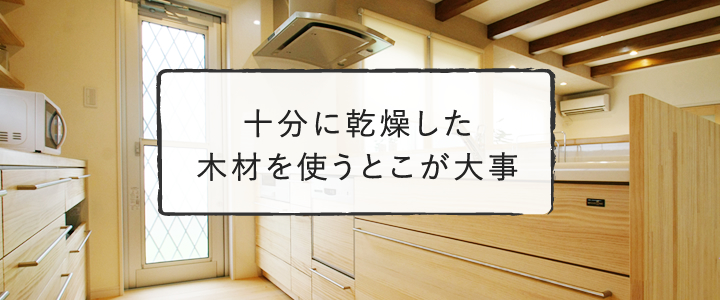

木は水分を多く含む素材で、通常、水分が少なくなるほど強度を増します。切り出した状態が最も水分量が多く、それから少しずつ水分が抜けていきます。
木に水分が多く残っていると、建てた後に水分が抜け、変壁の中の見えないところで水分が漂う可能性や反りなどの変形、割れを起こす恐れがあります。
柱、梁などの木造の構造材は、乾燥方法によって大きく3種類に分類されます。
- グリーン材:切ったままの状態の木材、非乾燥
- 自然乾燥材(AD材):天日干しした状態の木材
- 人工乾燥材(KD材):温度や湿度・風量を調整できる窯に入れ人工的に乾燥させた木材
人工乾燥材(KD材)は、天然乾燥材(AD材)に比べ木材の含水率を意図的に下げることができるため、天然乾燥材で起こりうる「建てたあとに水分が抜け、壁の中の見えないところで反りなどの変形、割れを起こす可能性」を極力下げることが可能です。そのため、私たちは基本的に人工乾燥材を使用しています。
なお、注入木材は木材内での水分量が多いため、使う場所を考える必要があります。
木の切り方で性質が変わる
丸い木を板状に加工するときに、その切り方で性質が大きく変わります。

板目 (一般的な木目といえばこちら)
- 丸太から多く取れる
- 複雑な木目、木の反り、ねじれが起きることがある、節がでやすい
- 繊維の層が水分を通しにくい
(例:餅をつくうす)
柾目
- 丸太から取れる量が限られる
- まっすぐな木目、木の変形が少なく、節がほぼ出ない
- 繊維の層が分断されるため、湿度を調整してくれる
(例:ご飯を一時保存するおひつ)